相続対策|生前贈与とは?メリットと注意点をわかりやすく解説
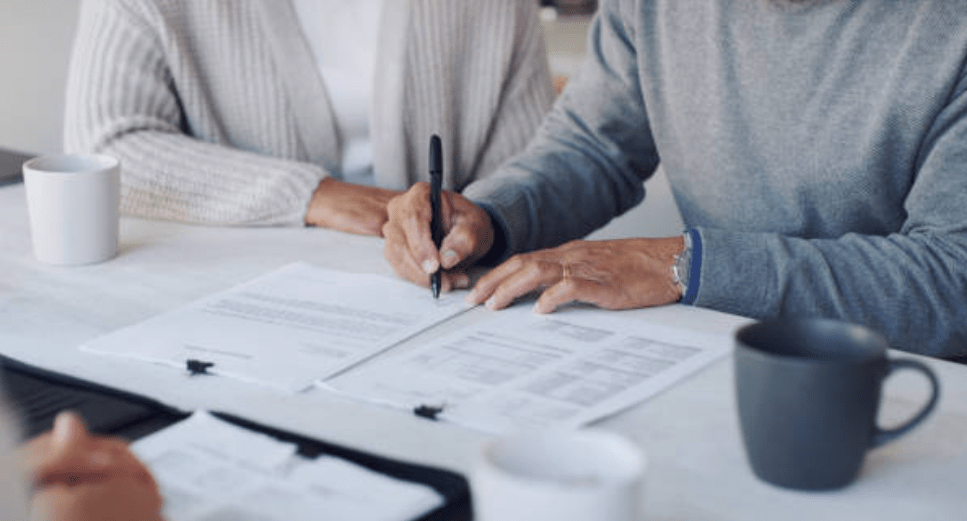
「生きているうちに子どもや孫に財産を渡したい」
「相続税を減らすために生前贈与を考えている」
このような声をよくお聞きします。
生前贈与(せいぜんぞうよ)は、相続が発生する前に財産を渡しておく方法で、上手に活用すれば相続税対策や家族間の意思疎通にも役立ちます。
ただし、税金や法的なルールも多く、慎重に進める必要がある手続きです。
今回は、生前贈与の基礎知識と注意点について、行政書士の視点からわかりやすくご紹介します。
1. 生前贈与とは?
生前贈与とは、ご自身が亡くなる前に、家族などに財産を無償で譲ることを言います。
現金や不動産、株式、自動車などさまざまな財産が対象になります。
主な目的:
- 相続税の節税対策
- 特定の家族に確実に財産を渡す
- 住宅取得や教育費の支援
- 将来の相続トラブルの予防
2. 贈与税の基礎知識
贈与を受けると、贈与税の課税対象になることがあります。
ただし、毎年の**基礎控除額(110万円)**以内であれば贈与税はかかりません。
例)年間110万円までの贈与:
- 贈与税は非課税
- 申告も基本的に不要(ただし複雑なケースでは必要)
このように、**毎年少しずつ贈与する(暦年贈与)**方法を「分けて渡す」ことで、長期的な節税が可能になります。
3. 生前贈与の主な方法
(1)暦年贈与
毎年110万円以内の贈与を繰り返す方法。
長期間をかけて計画的に財産を移すことができます。
(2)住宅取得等資金の贈与
一定の条件を満たす場合、**最大1,000万円(非課税)**まで贈与が可能(※制度によって変更あり)。
主に父母や祖父母からの贈与が対象。
(3)教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与(特例)
信託口座を使って、最大1,500万円(教育)・1,000万円(結婚・子育て)の贈与が非課税に。
※現在は制度縮小・終了の動きもあり、最新情報に注意が必要です。
4. 生前贈与の注意点
生前贈与にはメリットも多い反面、注意すべき落とし穴もあります。
(1)名義だけの「名義預金」はトラブルのもと
実際には親が管理しているのに、子ども名義にしただけの預金は「贈与」と認められず、相続財産として扱われることがあります。
➡ 贈与契約書を作成し、実際に相手に管理を任せることが重要です。
(2)相続開始前3年以内の贈与は「相続財産」にカウントされる
相続税の対象となる贈与のうち、死亡前3年以内の贈与は、相続財産として課税されます。
➡ 節税目的で贈与するなら、早めに計画的に実施することが大切です。
(3)不公平な贈与が後の争いにつながる
特定の子どもに多く渡していた場合、「特別受益」として相続分の調整が求められるケースも。
➡ 家族にあらかじめ伝えておくか、遺言書と併用することでトラブルを防ぎましょう。
5. 贈与契約書をきちんと作成しよう
贈与は「契約」であるため、口頭ではなく、書面にしておくことが望ましいです。
- 誰が、誰に、何を、いつ贈与したか
- 金額・物の明記
- 署名・捺印
これにより、名義預金や無効の主張を防ぎ、税務署への説明にも役立ちます。
行政書士に依頼することで、法的にも整った書面を作成できます。
まとめ|生前贈与は計画的に、慎重に進めましょう
生前贈与は、相続対策や家族への支援として非常に有効ですが、税務・法律の知識と計画性が不可欠です。
✅ 毎年110万円までの贈与は非課税
✅ 名義預金に注意、贈与契約書は必須
✅ 死亡3年以内の贈与は相続税の対象に
✅ 不公平な贈与は遺産トラブルの原因にも
✅ 遺言書や他の制度と組み合わせて総合的に検討を
糸賀行政書士事務所では、生前贈与のアドバイスから贈与契約書の作成、遺言との組み合わせまで、丁寧にサポートいたします。
「何から始めたらいいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
📞 ご相談はお気軽に
当事務所では、初回相談無料・土日対応可能です。
出雲市・松江市など島根県内全域対応。相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
メールで相談する
この記事を書いた人
行政書士 糸賀政貴(いとがまさき)
出雲市を拠点に活動する行政書士。
相続・遺言や建設業許可など、地域の皆さまの暮らしや事業に関わる手続きサポートを行っています。
「わかりやすく、ていねいに。」をモットーに、初めての方にも安心してご相談いただける対応を心がけています。

